|
|
| 第110回秦野物理サークル |
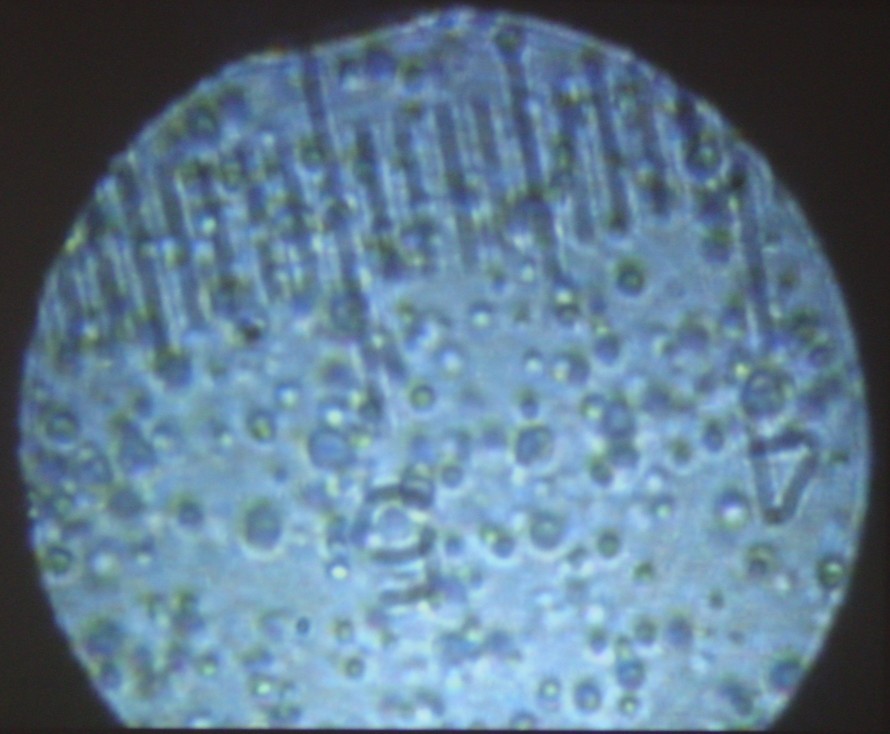 |
2012.5.20.発行
第110回秦野物理サークル報告
日時:2012年3月24日(土)14:00〜17:10
場所:伊勢原子ども科学館
参加者:稲葉一弘(伊勢原市役所)、岩瀬充璋(神奈川大学)、上田隆(かわさきアトム工房)、久保田信夫(立花学園)、倉田慎一(教育センター)、志村潤子((株)ナリカ)、鈴木孝雄(一般)、瀬戸誠(伊勢原子ども科学館)、塚本栄世(綾瀬西高校)
計9名
【1】発表項目
(1)「ブラウン運動」の動画の紹介(塚本栄世)...写真1〜写真3参照
(2)可視光通信(塚本栄世)...写真4〜写真7参照
(3)どこまで見えるか(鈴木孝雄)...写真8〜写真12参照
(4)ベンハムの独楽(倉田慎一)...写真13、写真14参照
(5)インターバルレコーダー「recolo」の紹介(倉田慎一)...写真15、写真16参照
(6)タコマ橋崩壊の動画の紹介(久保田信夫)...写真17〜写真20参照
(7)いろいろなゲジ虫の紹介(上田隆)...写真21〜写真28参照
(8)資料の紹介(岩瀬充璋)...図1、図2参照
【2】発表内容
(1)「ブラウン運動」の動画の紹介(塚本栄世)...写真1〜写真3参照
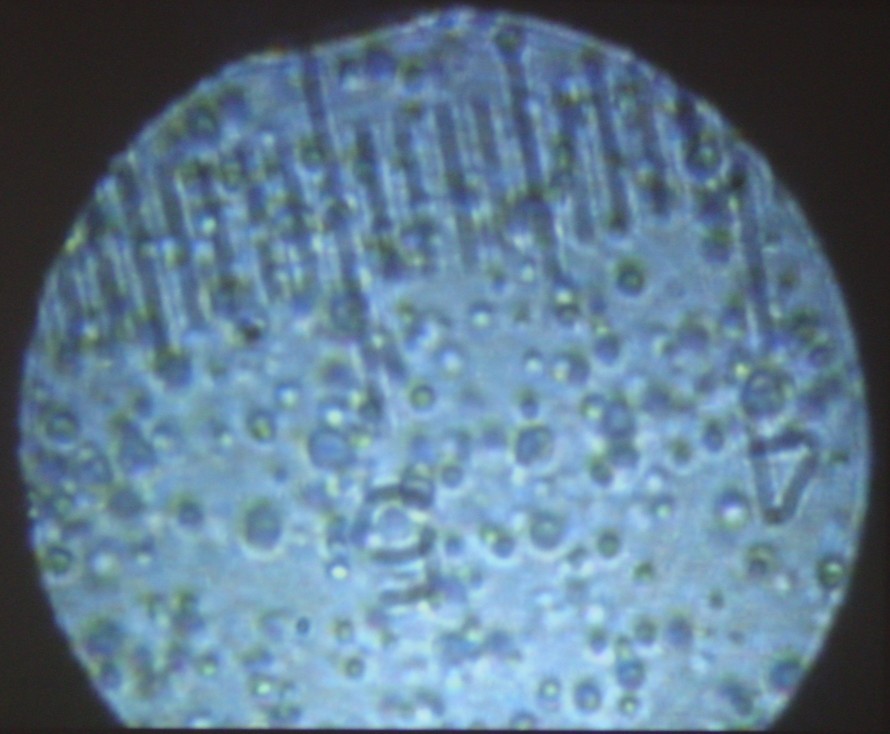 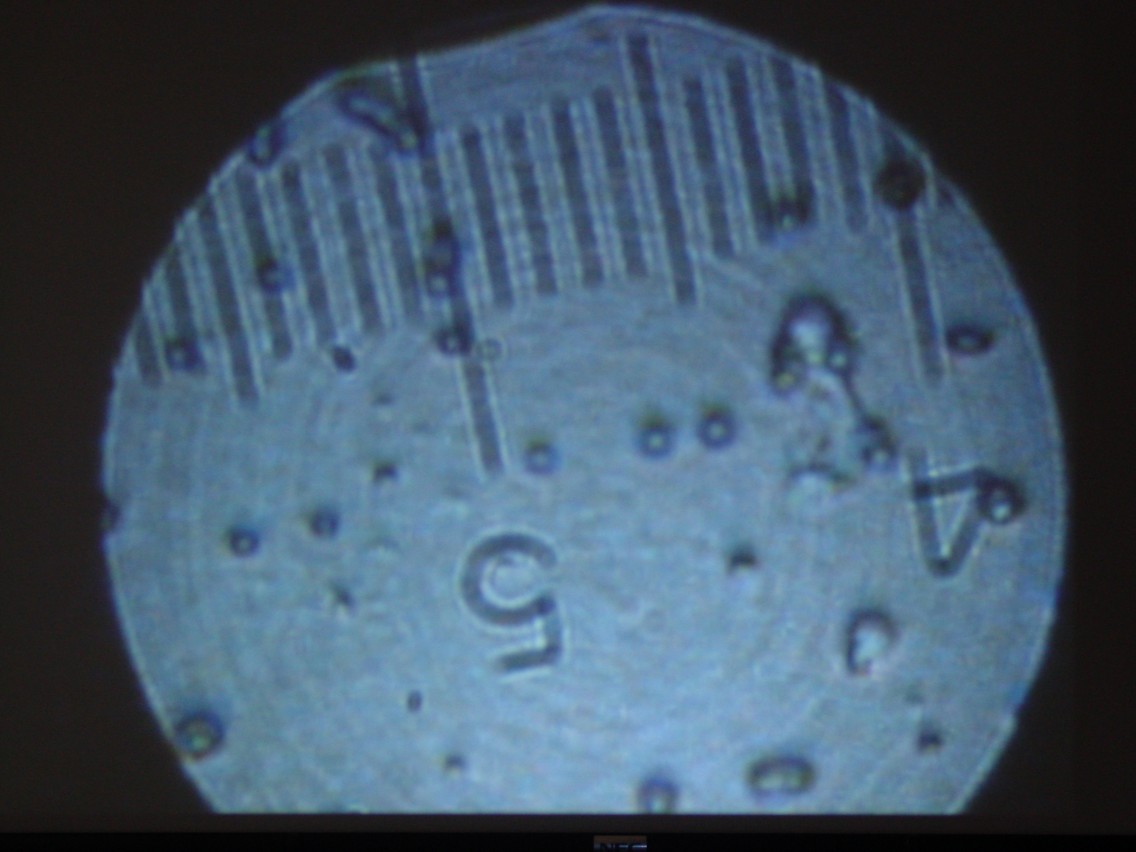
2006年の第79回〜第83回例会で報告した「ブラウン運動」(コーヒーに入れる「クリープ」の中に含まれる脂肪粒、プラスチック球、ゆりの花の花粉から飛び出した微粒子など)の動画をいくつか紹介しました。(写真3)はたまたま撮影できた微粒子の堆積現場です。
(2)可視光通信(塚本栄世)...写真4〜写真7参照
第108回例会(2011.11.26.実施済)で紹介されたRGBハイパワー白色LED(写真4参照、秋月電子通商から280円で入手できる)を利用して可視光通信をやってみました。まず、スイッチボックス(写真5参照)の3つの可変抵抗を調整してLEDから放射される光の色が白色になるようにします。次に、別々の音楽を演奏している3台のCDプレイヤーのヘッドホン端子から取り出した音楽の信号をスイッチボックスの中に配線した3つの可変抵抗に入れ、RGB各色のLEDにかかる電圧の値が音楽の信号に合わせて変化するようにします。その結果、肉眼では分かりませんが、RGB各色のLEDから放射される赤色、緑色、青色の光の強さがそれぞれの音楽(音楽R、音楽G、音楽Bと名付ける)に合わせて時間的に変化します。この各音楽の信号によって変調された赤色、緑色、青色の光(合わさって白色になっている)を1個の太陽電池に当てると、太陽電池に接続したパソコン用スピーカーから3つの音楽が同時に聞こえます。このとき、太陽電池の受光面を赤色のフィルターでおおうと、このフィルターを透過するのは赤色の光だけになる(写真6参照)ので、音楽Rだけがスピーカーから聞こえます。同様に、緑色のフィルター、青色のフィルターを使うと、それぞれ音楽Gだけ、音楽Bだけが聞こえます。
例会でこの実験を紹介しましたが、実験はうまくいきませんでした(事前に実験したときにはほぼうまくいっていたのですが...)その後、実験がうまくいかなかった原因を調べたところ、以下のようなことが分かりました。後日、再度実験してみたいと思っています。
①LEDから放射される光の色が不安定で、白色だった光が突然色が変化する現象が起きた。そのため、音楽R、音楽G、音楽Bのうちの一つが聞こえなくなったりした。
→単三アルカリ乾電池の電圧が低下していたことが原因。
...例会での発表に向けて最終的な調整をかなり長時間連続で行ない(例会の直前にも会場で最終的な調整を実施)、その間乾電池を新品と取り換えないで例会で発表した。
②赤色フィルター、緑色フィルター、青色フィルターを取換えながら実験したとき、音楽R、音楽G、音楽Bが混信して聞こえた。
→白色の実験台からの反射光が原因。
...事前に実験したときの実験台の色が黒色であったため、実験台からの反射光を減らす対策(例えば、黒い板の上で実験する、虫眼鏡で光を細く絞る等...)をとっていなかった。
...この点については、今後上記の対策だけではなく、以下のような基本的な検討をする必要がありそうである。
このRGBハイパワー白色LEDは光の広がりの角度が120°と非常に広いので、可視光通信の実験を行うためのLEDには適していないと思われます。第58,68,69,71,72回秦野物理サークル(2002年〜2004年)で紹介した「波の独立性を示す実験」や「光通信の実験」で使用した赤色および青色のLEDはいずれも光の広がりの角度が30°〜15°のものを使用し、さらにそれぞれのLEDに黒色のラシャ紙で作った円筒をかぶせて周囲に光が広がることを防止しました。この当時の実験で、別々の音楽の信号をのせた赤色と青色の光(虫眼鏡でさらに細く絞る)を光路の途中で交叉させ、パソコン用の2台のスピーカーそれぞれに接続した太陽電池で受光して2つの音楽が同時に聞こえるようにしてから、赤色と青色の光が交叉している(2つの光の波がお互いに通り抜けあう「波の独立性」)位置に赤色や青色のフィルターを置くと、片方の音楽だけを鳴らす(2チャンネルの可視光通信、写真7参照)ことに成功しています。従って、今後、可視光通信の実験を行うためのLEDとして光の広がりの角度がもっと狭いRGBハイパワー白色LEDを探す必要があると思われます。
(3)どこまで見えるか(鈴木孝雄)...写真8〜写真12参照
顕微鏡用のスライドガラスの上にピペットで水道水を一滴落とし(写真8参照)、コーヒーメーカーのヒーター(熱いコーヒーが冷めないように保温する部分)の上に載せてからスイッチを入れて加熱します(写真9参照)。すると、水道水の中の水がどんどん蒸発し、約80秒後には水がなくなってしまいます。スライドガラスが冷めてからその表面をよく見ると(スライドガラスの表面での光の反射を利用すると観察しやすい)、水滴の跡(白色の円形の輪、写真10参照)が残っています。この白く見えるものの正体はカルシウムの化合物です。ピペットから一滴落とした水滴の体積は約0.03mLといわれているそうですが、操作に慣れていない学生の場合は0.05mLとみていいそうです。そこで、簡単のためピペットから一滴落とした水滴の体積が0.1mLであるとして計算すると、水滴一滴の中に含まれる炭酸カルシウムを主とする物質の質量は10μgとなります。つまり、質量10μgの物質は「見える」ということになります。従って、さらに水滴一滴の10分の1の大きさの水滴を考えると、質量1μgの物質が「見える」と言えます。
続けて、ペットボトルに入れて持参した雨水で同様の実験をやったところ(写真11参照)、スライドガラスの表面に水滴の跡は見えません。それは雨水がとてもきれいだからです。雨水が汚れているのは降り始めだけで、ここ2〜3日雨が降り続いた後の雨水は特にとてもきれいで、上記の実験を行なってもスライドガラスの表面に水滴の跡は見えません。この現象は洗車の後でも見られ、水道水で洗車した場合は車の表面に白いものがボツボツと残ってしまいますが、外に出していた車が雨水で洗い流された場合は車の表面に白いものが残ってしまうことは一切なく、とてもきれいになります。
また、日本酒をスライドガラスの上にピペットで落としてから同様の実験をした結果が紹介されました。水が蒸発した後に茶色の円形の染みが残ります(写真12参照)。この円形の染みは日本酒の中に含まれている糖分がこげたものと考えられるとのこと。
例会では、水道水一滴をスライドガラスの上に載せてから水を蒸発させたときに残る水滴の跡(白色の円形の輪)は水滴の外側のみで、中心部分は色がつかないのはなぜかについていろいろ議論しましたが、結論は出ませんでした。
(4)ベンハムの独楽(倉田慎一)...写真13、写真14参照
CD−Rとビー玉を利用して製作したベンハムの独楽の紹介です。まず、ベンハムの独楽の白黒画像をパソコンでつくり、プリンターでCD−Rに直接ラベル印刷します。次に、CD−Rの中央部の穴にビー玉を接着剤で固定します(写真13参照)。CD−Rもビー玉も対称形なのでバランスが非常によく、いったん回すと非常に安定して長時間回ります(写真14参照)。
回転しているベンハムの独楽を見たとき、どのような色がついているように見えるかは個人差があるらしく、赤みをおびた色が見えたり、黄緑色や薄い茶色が見えたりするようです。また、日光の下で見る場合と蛍光灯の下で見る場合で色が違ってきます。
ベンハムの独楽の模様は白色と黒色のみです。それなのに、なぜ赤や黄緑色や薄い茶色が見えるかについては、まだ完全には解明されていないようです。
(5)インターバルレコーダー「recolo」の紹介(倉田慎一)
...写真15、写真16参照
「recolo(レコロ)」という名前のインターバルレコーダー(一定時間間隔で自動的に写真を撮影し、それらの静止画をつないで動画をつくるカメラ、写真15参照)が紹介されました。「KING JIM(キングジム)」というメーカーから6,930円(税込価格)で販売されています。設定できる時間間隔は3秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,1時間,6時間,12時間,24時間から選ぶことができ、また、1秒あたりのフレーム数も1〜24コマから選ぶことができます。このようなインターバルレコーダーを使って撮影した動画としてよく知られているのは、植物の成長を撮影し、早回しの画像として再生する動画ですが、植物が生長していく様子が本当によく分かります。
今回紹介されたのは、屋上に道路工事の現場などで使われるコーンを置き、時間の経過とともにその影がどのように変化していくかを時計の針の動きとあわせて撮影したものです。ちょうど春分の日をねらって撮影しているので、コーンの影の先端が西から東へ向かう一直線上を動く様子が(写真16)のようによく分かります。また、影の動く速さが朝と夕方には速く、正午は遅くなることもよく分かります。撮影の条件は、1分に1枚撮影し、1秒間に16フレーム表示するするようにしています。そして、「CANOPUS(カノープス)」という動画を編集するソフトを使って、影の先端を結ぶ補助線を引くと同時に、時計の長針が「0」になるごとに影の先端に赤丸を打つようにしています。
今後、フーコーの振り子の動きを撮影して時間を短縮して表示する動画や、魚眼レンズを使って月の動きを撮影し、時間を短縮して表示する動画をつくる予定とのこと。いろいろな応用がありそうです。
(6)インターネットで入手した動画「タコマ橋の崩壊」の紹介(久保田信夫)
...写真17〜写真20参照
インターネットで入手した動画を授業で使用する若い先生が多いので、自分も試してみたという報告です。物理の授業でちょうど共振をやっているときだったので、タコマ橋が崩壊する動画(写真17、写真18参照)をインターネットで検索してみたところ、いろいろな動画が公開されており、カルマンの渦に関するシミュレーション動画(写真19参照)とともに入手することができ、授業で好評であったとのこと。
タコマ橋は1938年から1940年にかけて建設された全長1600m、幅約12mの当時世界で3番目に長い吊り橋で、完成後4ヶ月で風速19m/sの風による共振(特に、ねじれ振動)によって崩壊しました。落橋後の原因調査で、橋の断面形状が薄い板状でしかも幅が狭いため横風を受けると橋の上下に生じた空気の渦(カルマンの渦)によって自励振動が発生することが分かったそうです。
共振によって大きな橋が崩壊する映像は迫力があり、共振現象の怖さを視覚を通して感覚的に理解する貴重な教材です。
また、ユーチューブ上で2012年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震に際に新宿センタービルが非常にゆっくりと大きく揺れている動画(写真20参照)が紹介されており、その動画も授業の中で生徒に見せたところ、その迫力に生徒が驚いていたとのこと。
(7)いろいろなゲジ虫の紹介(上田隆)...写真21〜写真28参照
「かわさきアトム工房」の活動の一例として、いろいろなタイプのゲジ虫(振動によって進む玩具)が紹介されました。まず、手作りのものを紹介する前に市販のゲジ虫がいくつか紹介されました。(写真21)は科学技術館の売店で販売されていたもので、長さ3cm程度の小型のものですが、非常になめらかに動きます。外見上振動している部分はなさそうですが、手で触ると振動しているものが中に入っているのが分かります。ディスク型の振動モーターが入っているのかもしれません。また、(写真22)は玩具メーカーから売り出されているもので、足の部分が非常にやわらかいゴムまたはプラスチックでできています。そして、このゲジ虫はかなり高速で動き、障害物にぶつかると向きを変えたり、ときどきはひっくり返ったりもします。
子どもたちを対象にした工作教室では、まずモーターを回転させることで振動を生み出すためにどのような工夫がされているかを示すために携帯電話機を分解したものを見せます。携帯電話機の中には長さ約1.5cm、直径約3mmの超小型モーターが入っていて(写真23、写真24参照)、携帯が着信するとこのモーターが回転し、モーターの回転軸についている形が対称形でないおもり(偏心おもり)のために振動が発生して携帯電話機が振動することを理解させます。
さらに、回転を振動に変えるのとは逆に振動を回転に変える仕組みの例として、お祭の屋台等でよく売られている「ガリガリ・プロペラ」を見せます。ガリガリ・プロペラは針金を巻きつけたわりばしの先端にプロペラを取り付けたもので、わりばしの側面に針金が巻きつけてあるために凸凹になっており、わりばしの側面を棒や電動歯ブラシでこすると、ガリガリ・プロペラ全体が振動してその振動が原因でプロペラが回転する(写真25参照)ことを理解させます。
工作教室では、下記のような工夫をしていろいろなタイプのゲジ虫を作ります。
・3枚のハレパネ(発泡スチロール製の板の表面に紙を接着したもの)を接着剤でくっつけて、断面の形が「コ」の字型の車体を作り、上の板に振動モーター(モーターの回転軸の先端には網戸の修理に使うチューブ...網を網戸の隙間に押し込んで固定するために使用)を取り付け、また、足になる2枚の板の断面(この部分が机の表面に接触する)にモールを貼り付けます。車体の上にはドラエモンの人形を取り付けたりして、遊びの要素も加えます(写真26参照)。また、(写真27)のように、洗濯バサミ、発泡スチロール球(これが車輪の役割をする)、竹ひごを組み合わせた車に電動歯ブラシを取り付けたタイプのものもあり、電動歯ブラシの振動が発泡スチロール球の回転に変わり、かなりなめらかに進みます。
・子どもたちがゲジ虫を実際に動かしてみるときには、(写真28)のようにひもを輪にしてその輪の中でゲジ虫が動くようにしたり、そのひもに沿ってゲジ虫が動くようにします。また、机の上に新聞紙をしくと、摩擦が大きくなりゲジ虫がよく動くようになる場合もあるとのこと。
・子どもたちがゲジ虫を作り出すと、それぞれの子どもがいろいろな工夫をする場合が多いようで、例えば、モーターの軸につけるおもりとして消しゴムを使う子どもがいるそうです。小さな工夫かもしれませんが、その子どもにとっては大きな工夫であり、そのような子ども自身の工夫を大事にして工作教室を続けているそうです。
(8)資料の紹介(岩瀬充璋)...図1、図2参照
「電解の基礎」という題名の資料が紹介されました。電解の本質は電気エネルギーを化学エネルギーに変換することであるととらえ、その観点から電位の変化を元に電気エネルギーを計算するという展開です。また、その中で「電気二重層」に関する解説もされており、今後いろいろ参考になりそうです。
次に、以下のような地震に関する二冊の本の紹介があり、地震が起きるメカニズムや関東大震災に関するいろいろなデータが紹介されました。
①「地震のはなし」 茂木 清夫(もぎ きよお)著 朝倉書店 2001.10.5.初版第1刷
②「関東大震災」 武村 雅之(たけむら まさゆき)著 鹿島出版会 2003.5.30.発行
関東地震(1923年に起きた関東大震災のこと)と兵庫県南部地震(1995年に起きた阪神淡路大震災のこと)の断層を比較すると、関東地震は断層の長さが130km、幅が70km、食い違い量が2.1m、マグニチュードは7.9で、兵庫県南部地震は断層の長さが50km、幅が15km、食い違い量が1.0mで、マグニチュードは7.3です。人的な被害の大きさは、関東地震は14万人(①の著書、②の著書では105,385名)、兵庫県南部地震は6,430名(①の著書、②の著書では5,502名)の方が亡くなり、兵庫県南部地震の場合は地震による震動によって家屋が倒壊しその後の火災によって焼死した方が多かったようですが、関東地震の場合は台風の余波による強風の影響もあって大火災が起きたために多数の方が亡くなったようです。
また、関東地震と兵庫県南部地震を断層について比較すると、関東地震は断層面の底角が20°の横すべり型ですが、兵庫県南部地震は断層面がほぼ鉛直の直下型です。南関東地域の沖合いには相模トラフという海溝があり、その付近でフィリピン海プレートが関東地方を乗せた岩盤である北米プレートの下にもぐり込んでおり、その動きが滑らかではなくときどきつっかかるときに地震が起きます。そのため、関東地震の際には神奈川県の西部から相模湾さらには千葉県の房総半島の先端部にかけての楕円形の広い地域(小田原、丹沢、鎌倉、横浜等の神奈川県、東京都、千葉県の南部を含む楕円形の範囲)の地下で大きなずれが起きたといえます。それに対して、兵庫県南部地震の断層面はほぼ鉛直方向で、地表に投影すれば神戸市の市街地から淡路島の西岸にかけての直線になります。
例会では、2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震が関東地震や兵庫県南部地震に比べて断層や地震の規模という点でどのような違いがあるのかについても検討しました。東北地方太平洋沖地震は太平洋プレートと北アメリカプレートの境界(日本海溝付近)での海溝型地震で、断層の長さが500km、幅が200kmと巨大で、マグニチュードは9.0です。東北地方太平洋沖地震によって放出されたエネルギーは関東地震の約45倍、兵庫県南部地震の約1450倍で、日本観測史上最大であると同時に、世界で1900年以降起きた地震の中でも4番目の巨大地震です。地震の振動による家屋等の倒壊に加えて、津波による甚大な被害が発生しました。犠牲者は死者、行方不明者あわせて約19,000人で、福島第一原子力発電所の事故や関東地方の埋立地での液状化現象も含めて岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県等の広範囲に人的、経済的な被害を与えました。
地震国である日本は過去に起きた地震について徹底した科学的な検証を行い、将来に起きるであろう地震に対する対策を練るべきであると思われます。このような分野に対して国を挙げて研究体制を整える必要があります。
【3】連絡先について
〒252−1123 神奈川県綾瀬市早川1485−1
神奈川県立綾瀬西高等学校 塚本栄世
TEL:0467−77−4251
FAX:0467−76−8199
【4】次回例会(第111回秦野物理サークル)について
5月26日(土)14:00〜17:00
場所は伊勢原子ども科学館です。
多くの方の参加をお待ちしています。
文責 塚本栄世
|
newpage1.htmlへのリンク
|
|

